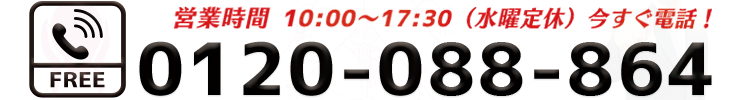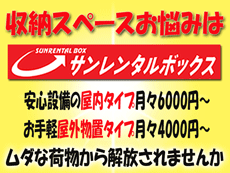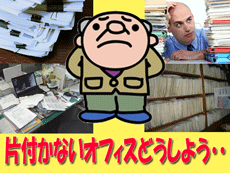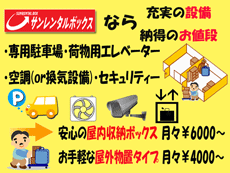宇都宮市はLRT(ライトライン)の2030年に街の西側への延伸開業に向け、迂回路整備を柱とする道路再編については用意周到ですが、肝心要のライトラインは宇都宮市が作成したイメージ図などが物議を呼んでいます!
過去ログ→【宇都宮市の駅西大通りはLRT整備で1車線化へ!】中心市街地の大改革でマイカー依存からの脱却は進むのか!?
過去ログ→【2050年頃を想定、JR宇都宮駅西口の将来メージを公表!】再開発のハードルが上がるなか、実現可能性を考えてみたら・・!?
「歩かない、ぬれない、待たせないが公共交通では大原則。十分な設備をお願いします。」
ライトラインの運行会社、宇都宮ライトレールの中尾正俊常務が強く訴えています。
→宇都宮LRT 駅西口停留場、朝夕混雑時への備え必至 ライトライン、30年延伸開業へ加速②(日本経済新聞)
確かに、このイメージ図の計画では、ホームのスペースが狭く、天候の影響も大きく受け、朝夕のラッシュ時に駅前が乗客でごった返し、大混乱になってしまいそうです。
イメージ図から実際の計画は大きく修正を余儀なくされそうです😅
建設費抑制を狙い小さな停留場を造り、想定外の乗客増加で改修を迫られたら、高架上の工事だけに費用と難易度がさらに上がってしまいそうです。
そして、ここへきて、人手不足と建築資材高騰だけでない、新たな問題も明るみになってきており、LRT西側延伸の計画は大きな困難を迎えそうです。
宇都宮LRTの延伸計画に暗雲
宇都宮市が進めるLRT(ライトライン)西側延伸の2030年開業計画において、建築コストの増加は、計画推進の深刻な懸念となり始めています。
そこへ来て、さらに、その整備に必要なコンクリート資材が確保できるかが不透明となってきているのです!
全国的な建設資材不足、特に軽量コンクリートの原材料である軽量骨材の供給不足が、この計画にも影を落としかねない状況となっています。
宇都宮LRTの西側延伸計画では、JR宇都宮駅西口停留場がペデストリアンデッキを解体した上で2階部分に建設される予定です。
このような高架構造では一般的に構造物の軽量化が望ましく、同様の公共交通インフラ事業では軽量コンクリートが使用されるケースがあります。
現在のコンクリート資材不足を考えると、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 構造設計の見直し必要性: 通常のコンクリートを使用した場合、構造物の自重が増加するため、支持部分や基礎の強化が必要になります。これは工期延長とコスト増加に直結します。
- 既存構造物との接続部分の課題: 駅西口の既存施設と接続する部分では、荷重計算の見直しが必要となり、追加的な補強工事が発生する可能性があります。
- 高架部の工期延長リスク: 建設資材の調達難により、工期の延長が避けられなくなる可能性があります。これにより予定されている2030年の開業時期が遅れるリスクが高まります。
こうした技術的課題が複合的に発生することで、宇都宮LRT西側延伸計画は当初の想定よりも大幅なコスト増と工期延長のリスクに直面しています。
特に、駅西口という市の玄関口での工事は市民生活にも影響を与えるため、建設資材の供給不足は単なる技術的問題を超えて、まちづくり全体の計画にも波及する可能性があるのです。
建設資材全体に波及する供給危機
日本の建設業界で直面している問題は、単に軽量骨材の不足だけではありません。
軽量骨材の供給逼迫は、コンクリート資材全体の需給バランスを崩す引き金となっています。
通常のコンクリートに使用される一般骨材(砂利・砂)も採掘規制の強化や環境問題により安定供給が難しくなっており、軽量骨材の不足はこの状況をさらに悪化させています。
軽量コンクリート用の資材が不足すると、高層ビル建設などの需要が通常コンクリート市場にシフトし、需給バランスを崩します。
その結果、生コンクリート全体の価格高騰と供給不足が更に生じてしまいます。
特に大都市の都市部では、再開発プロジェクトの集中により、建設資材全般の争奪戦が起きており、宇都宮のような地方都市のインフラ整備プロジェクトではコスト面で大都市に太刀打ちできず、今後、大きな影響を受けるのは避けられないでしょう。
生コンクリート業界の構造的危機
日本の生コンクリート業界は複合的な要因による深刻な供給危機に直面しています。
→都心の高層ビル建築に「砂利不足」の影 骨材価格が急騰(日本経済新聞)
この問題の直接的なきっかけは、軽量コンクリートの原料となる軽量骨材の供給不足です。
国内で唯一の生産会社となった日本メサライト工業(千葉県船橋市)は2024年7月に製造設備故障により数週間生産が停止し、再開後も「生産しても即出荷されてしまう状態」が続いています。
しかし、この問題はより根本的な構造変化に起因しています。
人工軽量骨材協会のデータによれば、全国の出荷量は2000年代初めの年間60万立方メートルから、近年では10万立方メートル強まで激減しました。
さらに2021年には頁岩(けつがん)の採掘コストや設備維持費の高騰により西日本の生産企業が撤退し、供給が1社に集中する脆弱な体制となりました。
この影響は軽量コンクリートだけにとどまらず、生コンクリート産業全体に波及しています。
→東京の生コン出荷、2月21%減少 軽量コン不足響く(日本経済新聞)
直近の状況を見ても、状況は悪化しており、東京地区の2025年2月の生コンクリート出荷量は前年同月比21.4%減の18万1797立方メートルと大幅に落ち込み、当初計画の25万立方メートルを27.3%も下回りました。
軽量骨材不足により需要が通常コンクリートに集中する一方で、型枠技術者の不足や2024年度からの建設現場の働き方改革による作業時間短縮も出荷減少に拍車をかけています。
特に懸念されるのは、・・・・・