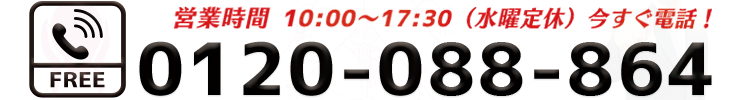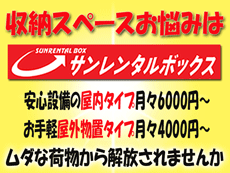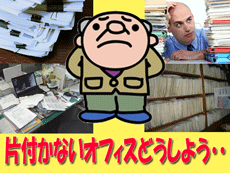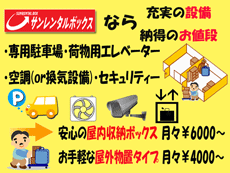ここ最近SNSの投稿で、宇都宮市の中心市街地におけるゴミ散乱問題の投稿が目立ち始めています。
過去に空きテナントだらけになってしまった、オリオン通りや周辺エリアは、飲食店街へと変貌し、再び人の流れが生まれ活気が出てきたのもつかの間、今度は治安やゴミ問題が顕在化してきています。
過去ログ→【にぎわい創出の場が変化する宇都宮の街!】東口駅前が街の顔に!?
過去ログ→【オリオン通りの治安が悪化!?】活気とのバランス!中心市街地のここ10年を振り返ってみたら!?
一方で、JR宇都宮駅周辺は着実に発展を続けています。
LRT整備と共に再開発されたJR宇都宮駅東口の駅ビル(ウツノミヤテラス)は空きテナントも概ね埋まり、人気ラーメン店(一風堂)の出店も決まり、盛り上がっています。
この対照的な状況は、宇都宮市の都市構造に何を物語っているのでしょうか。
中心市街地の「質的転換」がもたらす問題
かつてのオリオン通りは、商店街として多様な世代が日中から訪れるにぎやかな場所でした。
しかし、商業環境の変化や郊外型大型店の台頭により、空きテナントが目立つ状況に陥っていました。
その危機的状況を脱するために、飲食店を中心とした交流の場として再生が図られました。
特に居酒屋や飲み屋などの夜間型経済への転換は、短期的には人の流れを呼び戻す大きな効果をもたらしました。
この転換は中心市街地の「生き残り戦略」として一定の成果を上げたと言えます。
また、近年は中心市街地でマンション開発が相次ぎ、居住者数は増加傾向にあります。
新たな住民の流入は地域に活力をもたらす要素としてプラスに働いています。
しかし、中心市街地は「量」の問題から「質」の問題へと課題が変化しています。
以前は「いかに空きテナントを埋めるか」が最大の課題でしたが、今は「どのような店舗や機能で埋めるのが望ましいか」という質的な問題に直面しています。
単に埋まればよいというわけではなく、地域全体の環境や価値を高める機能配置が求められ始めています。
中心市街地の多くのビルは築年数が古く、設備も老朽化しています。
そのため、オフィスや最新の商業施設としての利用には多額の改修コストがかかります。
また、大規模な駐車場を確保ができないことから、商業施設を再び呼び戻すようなことも、困難です。
結果として、初期投資が比較的少なく済む飲食店、特に居酒屋などの夜間型施設が増加したのは、ある意味で合理的な市場反応でした。
しかし、夜間型経済への一極化は、以下のような問題を引き起こしています。
- 環境悪化(ゴミ問題、騒音、治安低下)
- 住環境と商業環境の軋轢(特に新規マンション住民と飲食店街)
- 日中経済の衰退(小売業、サービス業の撤退)
- コミュニティ意識の希薄化(新旧住民の交流不足)
特に深刻なのは、増加する居住者と飲み屋街の共存の難しさです。
新しいマンションに入居した住民は、静かで清潔な住環境を期待している一方で、夜間型経済は騒音やゴミ問題を生み出しがちです。
この軋轢は今後さらに大きくなる可能性があります。
JR宇都宮駅周辺の発展と「東への軸移動」
対照的に、JR宇都宮駅周辺は計画的な開発が進み、多様な都市機能が集積しています。
LRTの開業効果もあり、ウツノミヤテラスは空きテナントもほぼ埋まり、一風堂のような人気店の出店も決まるなど、明るい兆しが見えています。
この二つのエリアの明暗は、宇都宮市の都市軸が従来の「西(中心市街地)」から「東(JR駅周辺)」へと移動していることを示唆しています。
歴史的には東武宇都宮駅を中心とした都市構造だった宇都宮市が、JR宇都宮駅を中心とした構造へと転換しつつあります。
この「東への軸移動」は、現代の都市が直面する様々な課題への対応として理解できます。
限られた財政資源の中で都市機能を効率的に維持するには、一定の集約が必要です。
宇都宮市の場合、その「集約先」として市場原理的にJR宇都宮駅周辺が選ばれつつあると言えるでしょう。
JR宇都宮駅周辺が集約先として選ばれつつある背景には、複数の重要な要因が相互に関連しています。
まず、新幹線停車駅であることに加え、JR在来線の結節点であり、さらに新たに整備されたLRTの起点でもあるという交通アクセスの優位性が挙げられます。
この交通の利便性は、広域からの来訪者を集める強力な磁力となっており、商業・業務機能の集積を自然と促しています。
また、JR宇都宮駅周辺は、東口が再開発されたばかりであり、道路や広場などの公共空間が適切に配置され、歩行者にとっても快適な都市環境が形成されています。
さらに重要なのは、JR宇都宮駅と周辺に、・・・・・